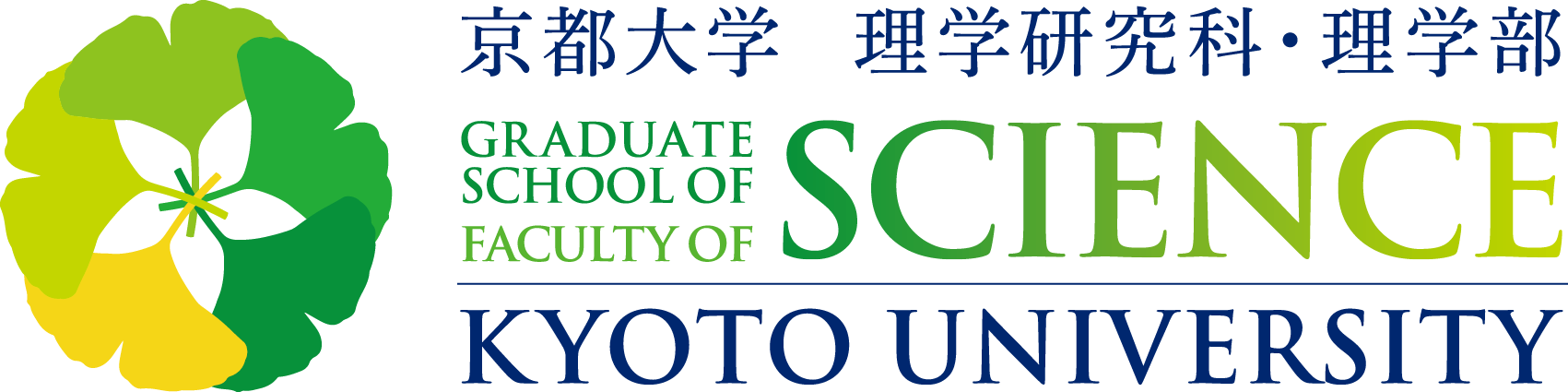生物科学専攻(動物学系)・教授 曽田 貞滋

新型コロナ流行が始まって丸2年がたつ。私の研究室(動物生態学)では、一人ひとりが異なる動物群を研究対象にしていて、大抵は野外調査とラボの実験を掛け持ちしているが、この3月に修士課程を修了する学生の中には、フィールドに行く機会が全くなかった学生もいる。私自身もいろいろなタイミングで国外、国内の調査を断念せざるを得ず、結果的にはゼロリスクに徹することになってしまった。一番の痛手は2019年秋に始めたばかりのアメリカでの周期ゼミ調査に行けなくなったことである。これは17年もの長い幼虫期からなる生活史の制御機構を解明するために、毎年、年齢の異なる幼虫を土中から掘り出して成長と遺伝子発現を調べる調査である。修士学生の一人もこの調査に参加するはずだった。幸い現地の共同研究者が一昨年,昨年と幼虫掘りをしてくれて最低限のサンプルは確保でき、学生はインフォマティクスに能力を発揮して首尾よく修論をまとめた。しかし学生は就職してしまうので、多分二度とない野外調査の機会を逃したことになる。
周期ゼミの生活史は徹底したリスク回避で成り立っている。幼虫は樹木の周りの固い土中に潜み、木の根から栄養の乏しい導管液を吸ってゆっくり成長する。はじめは小さすぎ,大きく食べごろになるのは最後の数年だけなので,モグラのような捕食者が好んで利用する餌とはならない。そして地上に出て成虫となり繁殖するのはわずか1ヶ月足らずの間である。おびただしい数の成虫が一斉に出現するため,鳥などの捕食者はすぐに飽食してしまい,多くは難を逃れる。周期ゼミはこうしたリスク回避、リスク最小化戦略で生き延びてきた。
ポストコロナの大学院生はどうなるのだろう。リスク回避の志向が強まり,野外に出かけ、自分の目で発見するような研究が衰退するのではないかと危惧する。私のようなロートルは仕方ないとしても,短い大学院生活を送る学生にたちには,ポストコロナの世界は再び開けたものであってほしいと切に願う。